よくある会社での話。ちいさな事業所ではその事業所にだけ通じる暗黙のルールがある。弱者は守られるべきもので、その分を他の人がカバーしていっているというのはどこでも あるもの。そして意外にも弱者ぶっている方が人生うまく生きていける。それに対して問題提起した本書は、こういうことを書く作家がいるんだとも感心した。最近の作家は、生きづらさばかり書いてくるものと思っていたから新鮮だった。非常に読みやすかった。
あるもの。そして意外にも弱者ぶっている方が人生うまく生きていける。それに対して問題提起した本書は、こういうことを書く作家がいるんだとも感心した。最近の作家は、生きづらさばかり書いてくるものと思っていたから新鮮だった。非常に読みやすかった。
★★★
高校の時、現代文学史のテキストに出てきていた久米正雄の「牛乳屋の兄弟」タイトルだけ覚えていたが、最近過去のそういった記憶の回収作業をしているところから、amazonでいろいろ検索してみたが、なんと絶版で手に入らない。40年前まではテキストの黒字になる ようなものがと驚いたが仕方ない。
ようなものがと驚いたが仕方ない。
いろいろ探していると「受験生の手記」が久米正雄氏の代表作らしい。それで、久米正雄作品集を買ってみた。読んで初めて大正時代を代表する人で芥川龍之介、菊池寛らと交流深く、漱石の娘に振られて、文学仲間の親友に取られてしまい、それを「破船」で心境を綴ったというのを知った。また、大正12年の震災時の話も興味深かった。このころの東大生は今の時代以上に人生を謳歌していたのがわかるしその中でも久米正雄は社交界で目立った人物であったというのも知った。そうした人生を鳥渡うらやましく思う。
父の死 手品師 競漕 流行火事 受験生の手記 金魚 桟道 他随筆 短歌
★★★
前から気になっていた「紀の川」を読んだ。時代の流れを紀の川を通じて感じる。どうしても時代の流れを感じる小説は悲しいものが多い。明治大正昭和でだいぶ日本国内の権力構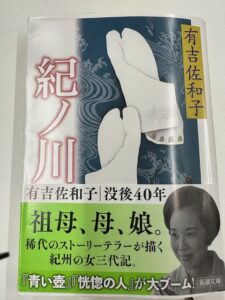 造は変わったが、実は続きの平成令和でももっともっと変化してきたものである。有吉佐和子が存命なら続きはどうなったか?
造は変わったが、実は続きの平成令和でももっともっと変化してきたものである。有吉佐和子が存命なら続きはどうなったか?
私の祖母は大正生まれだが、私の子供は令和世代である。それだけでも大正昭和平成令和と流れてきているのである。それぞれの時代背景の中でしか私たちは生きていけないのであり、昔を語っていては後れを取ってしまうのは必定。だけどどうしてだろう、昭和が無性に懐かしくてたまらなかったりするのである。変化の激しい時代。いいときは長くは続かないものである。それだけは間違いない。そして、老後がいろんな意味で豊かであれば全て吉だと思える。
★★★★★
菊池寛の「蘭学事始」から杉田玄白の「蘭学事始」を読むことにした。いろいろ発見があった。杉田玄白氏の初めての刊行本が「解体新書」であり「蘭学事始」は最晩年の83才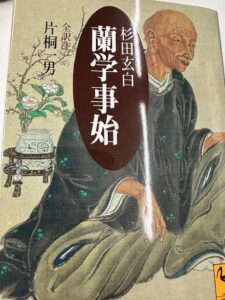 での稿であること。明治2年に刊行されるに至っては福沢諭吉の力添えがあったということ。「ターヘルアナトミア」の翻訳から始まった蘭学の流れを50年たった後で振り返り歴史的事実を後年に残したいというものであったこと。
での稿であること。明治2年に刊行されるに至っては福沢諭吉の力添えがあったということ。「ターヘルアナトミア」の翻訳から始まった蘭学の流れを50年たった後で振り返り歴史的事実を後年に残したいというものであったこと。
すでに学校教育で習っていたことは、恐らくこの本からのエピソードであろう。原文や解説が載っており現代訳のところは80ページ程ですぐ読んでしまうが読みごたえはあった。この本では、杉田玄白、前野良沢、中川淳庵の3人が中心で解体新書を訳したようなことを書いてあったが、現在中川淳庵の名は聞かない。世の中そんなものだろう。
この文庫は講談社学術文庫で本体価格1100円もする。価格は高いが、こういう社会的に意義のあるものを残してくれて現代でも読めるようにしていることをありがたく思うとともに日本の学術研究は大したものだと関心もした。
★★★★★
40年以上も前の話。もうほとんど忘れてしまっているのだがフランキー堺が菊池寛の役として出演していた映画を深夜テレビで見たことがある。面白おかしく描かれた作品で僕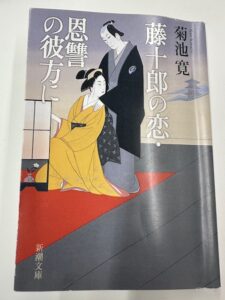 の中では、読みもしないで作家としての菊池寛の評価はそれほど高いものではなかった。中学の国語の先生が菊池寛の話をされ、彼の功績を黒板に列挙されていて作家というより企業家のイメージが強かったせいもあると思う。ところで、ここ1,2年で「恩を返す話」「忠直卿行状記」と読んで、作家としての偉大さを知った。そしてこの作品は菊池寛の代表作の一つでありタイトルだけ知っていただけに期待して読んだ。テンポよく話が展開し、終わりには思わず涙ぐんでしまう。ああやっぱり菊池寛って偉大だわと思わせる作品。★★★★★
の中では、読みもしないで作家としての菊池寛の評価はそれほど高いものではなかった。中学の国語の先生が菊池寛の話をされ、彼の功績を黒板に列挙されていて作家というより企業家のイメージが強かったせいもあると思う。ところで、ここ1,2年で「恩を返す話」「忠直卿行状記」と読んで、作家としての偉大さを知った。そしてこの作品は菊池寛の代表作の一つでありタイトルだけ知っていただけに期待して読んだ。テンポよく話が展開し、終わりには思わず涙ぐんでしまう。ああやっぱり菊池寛って偉大だわと思わせる作品。★★★★★