菊池寛の作品は、主人公の主観的思いと周りの思い。そして読者としての客観的な視点と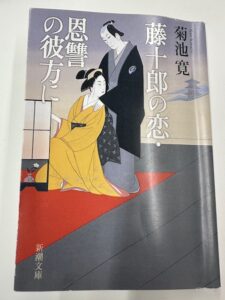 の相違を感じさせるものが多いと思っている。「忠直卿行状記」においても同様に感じつつ読んでいった。主人公の勘違いが浅はかに続くとばかり思っていたが途中で主人公が思い違いに気づいたことから、不幸な行動に至る結末であった。自己認識の面では非常に勉強になる。
の相違を感じさせるものが多いと思っている。「忠直卿行状記」においても同様に感じつつ読んでいった。主人公の勘違いが浅はかに続くとばかり思っていたが途中で主人公が思い違いに気づいたことから、不幸な行動に至る結末であった。自己認識の面では非常に勉強になる。
★★★★★
youtubeの本要約チャンネルが勝手に流れていて「ソクラステスの弁明」について語っていた。高校の頃「弁明」は軽く読んでいたが、改めて読みたくなった。
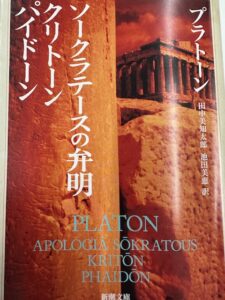 読んでいての感想は、まず、ソクラテスは現代では哲学者扱いだが、実態は宗教家であったのだろうということ。小さいころから神の声が聞こえていたと語っているし、デルフォイの神殿で、一番の知恵者だと言われたという話もそうである。自分を救世主と神の声を聴き宗教の祖となる人は多い。死から逃げずに信念を通して死を受け入れるのも自分の神を信じていたからだろうと思った。
読んでいての感想は、まず、ソクラテスは現代では哲学者扱いだが、実態は宗教家であったのだろうということ。小さいころから神の声が聞こえていたと語っているし、デルフォイの神殿で、一番の知恵者だと言われたという話もそうである。自分を救世主と神の声を聴き宗教の祖となる人は多い。死から逃げずに信念を通して死を受け入れるのも自分の神を信じていたからだろうと思った。
次に1回目の投票で死刑が決まってからの弁明において、お金を支払うと言いだしているということ。個人的には申し訳ないが命乞いの一種にも思え残念に感じた。
再度の投票で死刑が確定した後の演説が思ったより長いこと。現代の裁判で判決が下ったらそれで終わりなのに、死刑が確定した後に語る語る。長すぎだろと思った。
最後に訳者が田中美知太郎先生だったこと。
いろんなことを再認識した次第です。
★★★
朝倉先生の退任と次郎の諭旨退学をめぐる20日程度の騒動。下村湖人氏は、戦争に向かっていく時代にあたって、どうすればそれを避けることができるのかを戦後に次郎物語を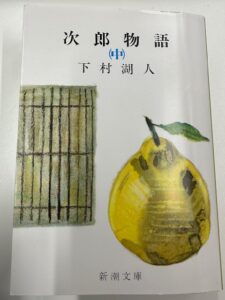 書いて今後の世の戒めにしたかったのではないかと思う。朝倉先生の白鳥会は、僕の若かりし時代の松下政経塾の小島直記先生の「伝記に学ぶ人物研究」を彷彿とさせた。小島先生からも配属将校に対する不満と言論弾圧に対する抵抗の話を聴いた。また、小島先生から将来の日本に対して、僕たちへの期待を感じるが、実際は先輩後輩を含め皆うまくいってない。つまらない政治家にもたくさんなっていると思う。非常に残念である。だめな政治家にならなかったことが皮肉なことにむしろ僕の誇りでもある。さて、次郎物語も次の5部で終わり。未完の作になっている。
書いて今後の世の戒めにしたかったのではないかと思う。朝倉先生の白鳥会は、僕の若かりし時代の松下政経塾の小島直記先生の「伝記に学ぶ人物研究」を彷彿とさせた。小島先生からも配属将校に対する不満と言論弾圧に対する抵抗の話を聴いた。また、小島先生から将来の日本に対して、僕たちへの期待を感じるが、実際は先輩後輩を含め皆うまくいってない。つまらない政治家にもたくさんなっていると思う。非常に残念である。だめな政治家にならなかったことが皮肉なことにむしろ僕の誇りでもある。さて、次郎物語も次の5部で終わり。未完の作になっている。
★★★★★
第2部は、母の死から中学に入学して朝倉先生に出合い次郎が変化してきたところまで。第一部は親向けの教育書として書かれたらしい。第2部の朝倉先生のモ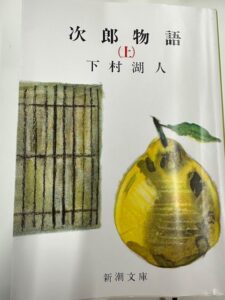 デルは下村湖人氏そのものということである。朝倉先生との出会いで変貌する次郎は、作家の青年の理想像であろうと思う。私も恩師から、学校に進学したら3つの出会いを果たすようにと言われたことを思い出した。「学問との出会い」「良き友人との出会い」「良き師」との出会い。2部の後半は、いかにもそれが強く出すぎていて、ちょっと抵抗も感じた。3部以降あまり、押しつけ感が強くなれば嫌だなあと感じる。それでも十分楽しめる。
デルは下村湖人氏そのものということである。朝倉先生との出会いで変貌する次郎は、作家の青年の理想像であろうと思う。私も恩師から、学校に進学したら3つの出会いを果たすようにと言われたことを思い出した。「学問との出会い」「良き友人との出会い」「良き師」との出会い。2部の後半は、いかにもそれが強く出すぎていて、ちょっと抵抗も感じた。3部以降あまり、押しつけ感が強くなれば嫌だなあと感じる。それでも十分楽しめる。
中学の頃読んだが旧制中学の位置づけがわからず読み方も浅かったかもしれないと思う。
★★★★
「路傍の石」を読んでいたら、「次郎物語」が読みたくなった。これらは教養小説とよばれていることを初めて知った。教養小説とは、主人公がさまざまな体験を通して内面的に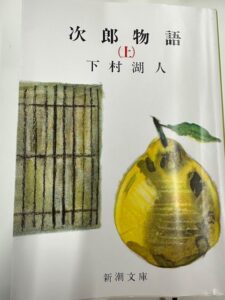 成長していく過程を描く小説のことをいうらしい。これら2冊はその代表作品のよう。1部から5部まで分かれているが、今回は新潮文庫を選び上中下巻の3冊を読むことに。
成長していく過程を描く小説のことをいうらしい。これら2冊はその代表作品のよう。1部から5部まで分かれているが、今回は新潮文庫を選び上中下巻の3冊を読むことに。
第一部は、出生から母の死まで。中学の頃読んではいたが、すっかり忘れ去られていた。里子に出された次郎を取り巻く複雑な人間関係は、田舎の親戚の多い家では結構理解できる話ではないだろうか、私の場合は、父の実家を思い出しつつ読み進んだ。自分の小さい頃の思い出などとうの昔に忘れ去られているものだが、読んでいるといろいろ思い出してくるところがあ り。面白い。
り。面白い。
中学時代に読んでいてよかったと思う。私の記憶では2度読んだつもりであったが、ひょっとすると1回だけかもしれない。中学の時は河出書房グリーン版日本文学全集で読んだ。けっこう読みごたえがあったのを覚えている。
★★★★★
中学受験の国語の問題に吾一少年が出てきて、塾の先生が路傍の石の話をした記憶がある。そんなに頻繁に出てきたものではなくて多分路傍の石の吾一少年の問題に出会ったのは2回程度だと思うが、「路傍の石」「吾一」の言葉が強烈で、なんだか小学生の私にとっては立ち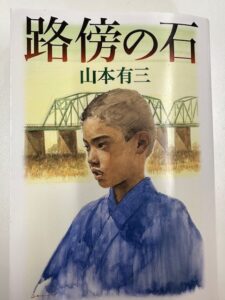 はだかる巨人のように思えて心に残り続けた。
はだかる巨人のように思えて心に残り続けた。
それから40年以上経過した今、読んだわけだが、何をそんなに恐れていたのだろう?朝日新聞の連載ではないか?しかも未完であり、これからの成長が楽しみというところで終わっている。ちょっと拍子抜けもしたが、とにかく読了したことで巨人に勝ったような一人で満足しきっている自分がいる。でも、本音いうともっと早く読んでおけば影におびえることもなかったと思う。そして、不思議なもので、下村湖人の「次郎物語」を久しぶりに読みたくなった。
★★★★★
「西門志織のおはなし千一夜」の放送がクリスマスイブの日にあったので、クリスマスに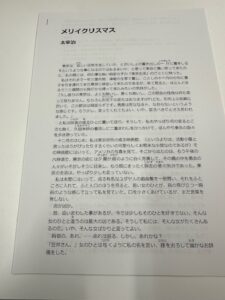 ちなんだ、作品になった。クリスマスと言えば、それっぽい作品はいくつもあるだろうけど太宰治の作品はいわば真逆に当たると思う。モブさんの高校生の頃、太宰治の作品は結構読んでいたから恐らくこの作品も読んでいただろう。でも、ほとんど心にも頭にも残っていなかった。
ちなんだ、作品になった。クリスマスと言えば、それっぽい作品はいくつもあるだろうけど太宰治の作品はいわば真逆に当たると思う。モブさんの高校生の頃、太宰治の作品は結構読んでいたから恐らくこの作品も読んでいただろう。でも、ほとんど心にも頭にも残っていなかった。
せっかくの機会だからと読んでみると。クリスマスイブの日にこれはこれでいい作品だと思えるようになった。
戦後すぐの日本人の多くは、きっと多くのトラウマを抱えていたことだろう。今日の個々人が抱えている問題など小さいものだと感じるかもしれない。そういうことを感じた。また、声優の西門詩織さんの声の使い分けや作品を理解した上での演技が秀逸である。メリイクリスマスの動画は敢えて鰻としてみた。
★★★★★
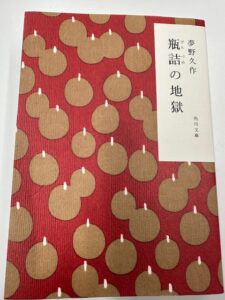 久しぶりに面白い作品に出合った。夢野久作氏の作品は全体的に好きなのだが、ぐっと引き付けられた。角川文庫の瓶詰の地獄の中の短編作品の中で一番だろう。
久しぶりに面白い作品に出合った。夢野久作氏の作品は全体的に好きなのだが、ぐっと引き付けられた。角川文庫の瓶詰の地獄の中の短編作品の中で一番だろう。
いろいろ考察をしたいところである。ネットで感想をいろいろ探したが他の作品と違って考察はあまり出てこない。単純に交錯した世界観を楽しみにした方がいいということかも。
ちなみに私の解釈は、標本室に行ったところまでは現実で、あとは午前4時ごろ起きて殺人事件の騒がしい状況を寝ぼけていて感じていた。2度寝して自分が犯人ではないかという夢を見て夢の中で副院長に責められる。明け方起きて、現実の殺人事件の様子を聞いた。
それにしてもなぜ院長が出てこなかったのかが気がかりであった。逆に言うと副院長とする必要性があったのか?
★★★★★
夢野久作のビール会社征伐がおもしろくて、夢野久作の作品を改めて読んでみようかと思った。今回は角川文庫の「瓶詰の地獄」を購入。瓶詰の地獄は、以前かつしかFMで「深川芹亜のradioclub.jp」を放送していた時、深川さんがおはなし千一夜として一部朗読したことがあるので、全文を読んでみたいと思っていたので楽しみにしていたものです。
今読んでみると、そこまで真剣に考えなくともと思ったりする。
★★★